この物語はフィクションです。実在の人物や団体などとは関係ありません。
プロローグ
 なぜだ。どうして、こんなにもヘボい手ばかりなのに、アイツは勝ち続けることができるんだ。
なぜだ。どうして、こんなにもヘボい手ばかりなのに、アイツは勝ち続けることができるんだ。
山崎祐樹は、冷たいプラスチックのマウスを握りしめながら、目の前のモニターに映るネット将棋の盤面を凝視した。相手は「将棋道場」のレーティングにおいて、彼の自己ベストを遥かに上回る数値を叩き出している無名のプレイヤー。その連勝記録は不気味なほど途切れることがない。過去の対局ログを辿れば、プロ棋士が相手であった局面も確かに存在した。だが、その全ての戦績が「無敗」で塗り固められている。
この不滅の記録が、彼の抱える根源的な疑問を刺激してやまない。
「例えば、この将棋だ」
彼は、特定の局面で相手が指した一手——素人でもしないような凡手——を反芻する。定石を無視し、大局的な優位を投げ捨てるかのような、経験者が決して選ばないはずの劣悪な手。その一手を指し、それなのに相手が勝利している。彼の脳は、この論理の矛盾を処理しきれない。
「もちろん、こういうことはよくある。ミスを重ねて、たまたま勝つこともある。だが、これを含めて全て無敗だという事実が、この結果を単なる偶然だと受け入れることを拒否させる」
もし、相手がミスを重ねなければ、この将棋は確実に負けていたはずだ。この結末は本当に偶然の産物なのか?あるいは、彼には何か別の、我々の視点を超越した力があるのだろうか。
彼の思考は、将棋というゲームの根本原理へと引き戻される。
二人零和有限確定完全情報ゲーム。
この概念が持つ絶対的な論理性が、彼の頭の中で、冷たく、確固たる真理として響き渡る。プレイヤーの数は二人。勝者と敗者の利得は完全に相殺される(零和)。ゲームは必ず有限の手番で終了する(有限)。サイコロのような運の要素は一切ない(確定)。そして、盤面の情報は両プレイヤーに完全に開示されている(完全情報)。チェスや将棋、オセロといったボードゲームの多くがこれに該当する。
このカテゴリーに属するゲームの最大の特徴は、理論上は完全な先読みが可能であることだ。双方のプレイヤーが常に最善手を指し続ければ、必ず結果(先手必勝か、後手必勝か、引き分けか)が決まる。現実には、選択肢が指数関数的に増大するため、人間による完全な先読みは不可能となり、そこに「ゲーム」としての面白さが生まれる。
しかし、この無敗のプレイヤーは、その理論上の壁を、まるで嘲笑うかのように打ち破っている。
「次の手を、何を指すか分かっているとでも言うのか?どうやって?」
それは将棋ではない。それは未来視、あるいは盤上を超えた情報の独占だ。そして、最も恐ろしい問いが、彼の確信を揺さぶる。
「そもそも、お前は、相手が何を指すか分かれば勝てるのか?」
もし彼がヘボ手を指すにもかかわらず無敗だとしたら、それは将棋の定石や強さの基準そのものが、彼の支配するロジックの前では無力であることを意味するのではないか。
二人零和有限確定完全情報ゲーム
二人:プレイヤーの数が二人
零和:プレイヤー間の利害が完全に対立し、一方のプレイヤーが利得を得ると、それと同量の損害が他方のプレイヤーに降りかかる
有限:ゲームが必ず有限の手番で終了する
確定:サイコロのようなランダムな要素が存在しない
完全情報:全ての情報が両方のプレイヤーに公開されている
という特徴を満たすゲームのことでチェス・将棋・オセロなど、運に左右されないボードゲームの多くが二人零和有限確定完全情報ゲームに相当する。二人零和有限確定完全情報ゲームの特徴は、理論上は完全な先読みが可能であり、双方のプレーヤーが最善手を指せば、必ず先手必勝か後手必勝か引き分けかが決まるという点である。実際には選択肢が多くなると完全な先読みを人間が行う事は困難であるため、ゲームとして成立する。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8C%E4%BA%BA%E9%9B%B6%E5%92%8C%E6%9C%89%E9%99%90%E7%A2%BA%E5%AE%9A%E5%AE%8C%E5%85%A8%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0
1.発症
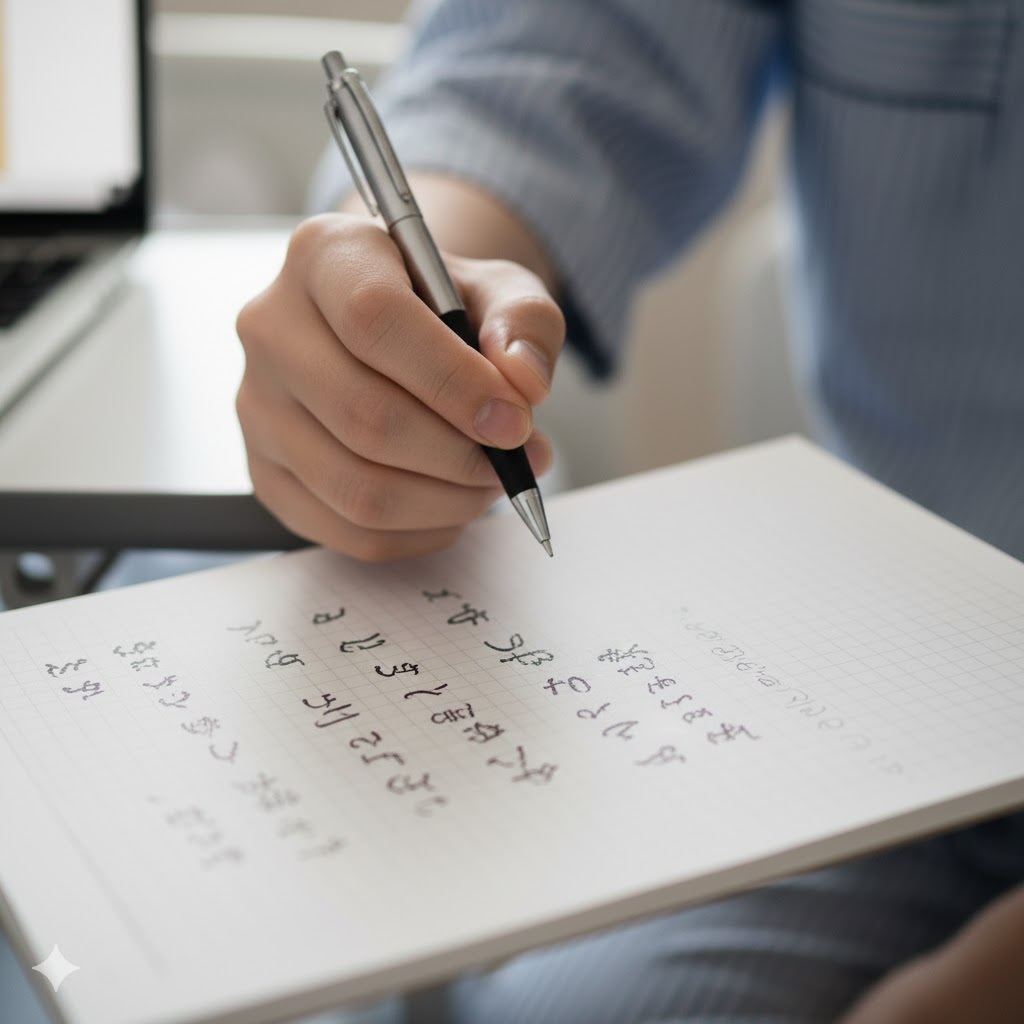
「多発性硬化症の疑いがあります」
耳に届いたその言葉は、今まで一度も聞いたことのない言葉で、何の実感もわかなかった。
異常を感じ始めたのは、数日前から始まった右手の中指の、微かで持続的な痺れだった。単なる寝不足か、仕事の疲労だろうと高をくくっていた。しかし、念のため近所の病院を訪れ、MRI画像を前にして、医師はその病名を告げた。
「ご覧ください、頚髄——首に近い脊髄の一部ですね——ここに、白い影が確認できます。この影響で、右手の神経がおかしくなっている可能性が高いです」
彼の体の、ごく一部、頭に近い重要な神経の中枢に、異物が宿っている。医師はすぐに大学病院への紹介状を準備してくれた。その迅速な対応は、何か悪い病気なのかなと感じさせた。
大学病院側が受け入れ態勢を整えるまでの約一週間、彼は自宅で安静にしていた。少し痺れる程度で比較的元気だったのでむしろいい休暇だとさえ感じていた。しかし、その安静期間で症状が次第に進行していった。
初めは中指だけだった痺れは、やがて右腕全体へと広がった。指先の細かい感覚は消え失せ、腕全体が異物のように重く、他人のものであるかのような不快感を伴う。さらに、首を少しでも動かそうとすると、頭蓋の奥、脊椎の根元から、何とも表現しがたい鋭い激痛が走り抜けた。
痺れによって、文字をまともに書くことができない。 得意だったはずのピアノの鍵盤を、もはや正確に叩くことができない。 長年の経験で身につけたそろばんの珠を、弾く感覚も一瞬で失われた。
長年積み重ねてきた技術、習慣、そして自信。その全てが、音を立てずに、急速に瓦解していく。
その時、中学の国語で暗唱させられた『平家物語』の冒頭の一節が、深く錆びついた鉄鎖のように、彼の脳裏を縛り付けた。
祗園精舎の鐘の声、
諸行無常の響きあり。
娑羅双樹の花の色、
盛者必衰の理をあらわす
まさに、この世のすべての現象は絶えず変化していき、どんなに勢いが盛んな者も必ず衰える。その理不屈の法則を、今、自分の身体で体現しているのだと思った。
そして、入院の日となった。
2.入院
「山崎祐樹さん」
看護師の呼ぶ声は、早朝の静寂に沈む病院のフロアに、わずかに緊張を伴って響いた。名前を確認し、彼は親に運転してもらった車から降り、入院棟へと足を踏み入れる。
ここ京大病院は、実家から高速を使って九十分ほどの距離にある。両親も頻繁には見舞いに来られないだろう。だが、国内でも有数の大病院であり、設備の充実度は申し分ない。特に、病院自体が京都の主要な観光地の真ん中に位置しているため、最低限の環境が整っていること自体が、この先の閉鎖的な入院生活における、数少ない希望の一つだった。
病気が発症したタイミングは、茨城県の大手企業で五年目を迎えようとしていた時期、東北地方での大地震により会社が一時的に休みになり、実家に帰省した時だった。それまでは週六日、日付が変わるまで働き詰めの生活。肉体的な疲労は自覚していなかったが、急に仕事が途切れ、張り詰めていた緊張の糸が一気に緩んだ。その気の緩みが、病という形で出現したのかもしれない——彼はそう考えずにはいられなかった。
上司には既に病状と休職の旨を連絡済みだ。彼は、抱えていた仕事の引継ぎのために、遠路はるばる茨城からこの京大病院まで来てくれるという。その責任感と、自分の人生が突如として中断されたことへの複雑な感情が、彼の胸に渦巻いた。
入院手続きを終え、彼は病室へ案内された。そこは六人部屋の大部屋で、年配の患者から若い患者まで、様々な顔ぶれが見える。彼は特に誰とも挨拶を交わすことなく、案内された窓際のベッドへと進んだ。窓からは、都会の喧騒が遠く聞こえる。
ちょうど正午の時間帯で、最初のイベントである昼食のワゴンが運ばれてきた。しかし、彼がそれ以上に優先すべき課題は、この先待ち受ける暇との戦いだった。
体調は優れないが、この一週間で、外部との情報が遮断されることの恐ろしさを痛感していた。彼は入院準備の際、ノートパソコンとポータブルWiFiの契約を済ませていた。病室での電子機器使用のルールは曖昧だったが、彼は敢えて確認せず、素知らぬ顔でベッドのサイドテーブルにパソコンを広げ、起動させた。
カチリ、と静かに開いたパソコンの蓋。
都会の真ん中にあるためか、ポータブルWiFiの接続は驚くほど快調で、実家に引いていた古いADSLよりもはるかに高速な通信速度を叩き出した。ネットワークランプが青く点滅するのを見て、彼はわずかに安堵の息を漏らした。
これで、少なくとも外界との繋がりと、将棋という精神的な戦場だけは確保できた。快適な入院ライフになる保証はないが、精神的な孤立だけは避けられそうだ。
3.将棋
 とはいえ、右腕全体に残る不快なしびれは、彼から多くの自由を奪っていた。
とはいえ、右腕全体に残る不快なしびれは、彼から多くの自由を奪っていた。
タイピングのような両手の細かい作業はすぐに指が疲労し、神経を逆撫でされているかのような倦怠感が肩から指先へと蓄積する。そのため、パソコンでの作業は自然と、動画視聴やウェブサイトのネットサーフィンなど、主にマウス操作を中心とする作業がメインになった。
その中でも、彼にとって最高の暇つぶし、そして現実からの逃避場所となったのが、ネット将棋だ。
彼は「将棋道場」というオンライン対局サイトに深く没頭した。常時二千人から三千人のユーザーが接続しており、彼の棋力——大学時代は将棋部に所属し、将棋センターで手合いを付けるアルバイトをしていたほどの腕前——と近しいユーザーも一定数いるため、対局相手に困ることは一切ない。
将棋は、彼にとって下手の横好きというには深すぎる、人生の一部だった。就職後も会社の将棋部に所属し、土日には一日中オンライン将棋を指し続けることさえあった。その愛着は、右腕の痺れで将棋盤の駒を物理的に動かすことすら困難になった今でも、全く衰えていなかった。
気分は決して快調とは言えないが、暇を持て余すほどには元気だ。彼は点滴を受け、検査の合間を縫っては、ただひたすらに将棋道場で対局を続けた。指先が痺れていても、マウス操作さえできれば、思考と戦略の領域に没頭できる。彼の内なるエネルギーは、この二人零和有限確定完全情報ゲームの盤上で消費され、現実の苦痛を一時的に麻痺させた。
4.発端
様々な神経内科の検査を受け、主病に対する点滴治療を開始してから、いつの間にか入院して二週間が経過した。
二週間も同じ病棟で過ごすと、環境の雰囲気にも慣れ、居心地の良ささえ感じ始める。暇を持て余して大変かと思われるかもしれないが、彼には将棋道場をはじめとする高速なインターネット環境があった。外界と繋がり、思考の戦場を維持できる限り、辛さは微塵も感じなかった。
彼が入院しているのは神経内科のエリアだが、病棟全体には、神経系の疾患を持つ患者だけでなく、交通事故で重い骨折をした人など、様々な病状の患者が混在していた。いずれにしても車椅子を利用する方が多く、病棟の長い廊下を散歩していると、多くの車椅子と静かにすれ違う。その移動音が、病棟特有の、抑揚のない日常の音の一部だった。
また、このエリアのもう一つの特徴として、夜中に突然大声でわめきだす高齢の女性患者がいることだ。幸い同じ部屋ではないため、その声は遮られて遠く聞こえる程度だが、同じ病室の患者たちはさぞ大変だろうと想像した。看護師たちが動揺することなく、慣れた手つきで静かに対応している様子には、日々のプロフェッショナルな対応に感心させられた。
基本的には相部屋ではあるが、患者間の会話はそれほど多くない。家族や友人の定期的あるいは頻繁な見舞いがあるため、患者同士で深い交流を求める必要性が低いのだ。とはいえ、ベッドを仕切るカーテンは日中はほとんど開け放たれており、トイレや洗面所で出合い頭になったりすると、愛想のいい、あるいは寂しがり屋の高齢の男性患者が、たわいのない雑談を投げかけてくれることもあった。
そうした日常の繰り返しの中で、彼自身の内にあった他者への防衛的な壁も少しずつ低くなっていった。知らないうちに、自分から人に話しかけることへのハードルも下がってきていた。
全身麻酔を伴う手術を受けるような患者も含め、多くの入院患者が一週間程度で退院していく中、二週間も入院している彼は、この病棟ではすでに「大先輩」のような立ち位置になっていた。
そんな中、ちょうど彼と同じくらいの、おそらく二十代の男性が、彼の向かい側のベッドに入院してきた。
彼は看護師から、ベッド周りの医療機器の使い方や、入院生活の細かなルールについて説明を受けている。彼は、もう何度も聞いた内容を、どこか懐かしさとともに聞いていた。
新しい患者がふと視線を向けた。山崎と目が合った。
彼は軽く会釈を返した。彼の視線が、山崎のサイドテーブルにしっかりセットされたノートパソコンへと一瞬向けられたのを、山崎は見逃さなかった。何かしらの作業をする人間だと察したのだろうか。彼はすぐに自身のバッグから、真新しいノートパソコンを取り出し、山崎と同じように、サイドテーブルにセッティングし始めた。
二人の孤独なプレイヤーが、情報と思考の領域を確保しようとしている。静かで微かな、しかし決定的な始まりだった。
(続く)


コメント